人事異動・組織改編(改正)とは?
企業が継続的に成長し、変化する市場環境や経営戦略に柔軟に対応していくためには、人材の適正配置と組織体制の見直しが欠かせません。
その中核をなすのが「人事異動」と「組織改編(または組織改正)」です。
人事異動とは?
人事異動とは、従業員の配置転換や職務変更を行うことを指します。
目的や内容によって、さまざまな種類があります。
主な人事異動の例
- 部署異動:営業部から企画部など、部署単位の移動
- 役職変更:昇進・降格・役職の新設など
- 勤務地変更(転勤):地域や支店の変更
- 出向・転籍:グループ企業や関連会社への異動
人事異動は、業務上の必要性に基づき企業が命じることが多く、人材育成・適材適所・組織の活性化といった観点で行われます。
組織改編(改正)とは?
組織改編(または組織改正)とは、企業の組織構造や部門体制そのものを見直す取り組みです。
よくある組織改編の例
- 事業部制から本部制への移行
- 新規事業部門の新設
- 既存部門の統廃合(例:営業一部と営業二部の統合)
- 管理職層の再構成や階層の簡素化
組織改編は、経営方針の変更や事業再編、働き方改革への対応などを目的に実施され、人事異動と連動するケースが非常に多いのが特徴です。
なぜ今、注目されているのか?
- 人材の流動性向上:企業内でも、社外でも「柔軟なキャリア形成」が求められる時代
- 事業ポートフォリオの見直し:不確実な経営環境の中で、収益性や戦略性を重視した構造改革が進行中
- 働き方の多様化:リモートワークやジョブ型雇用など、新たな働き方に対応するための体制変更が必要
こうした背景のもと、人事異動や組織改編の回数・頻度は増加傾向にあり、企業にはよりスムーズで透明性のある運用体制が求められています。
内示とは?人事異動前の重要なステップ
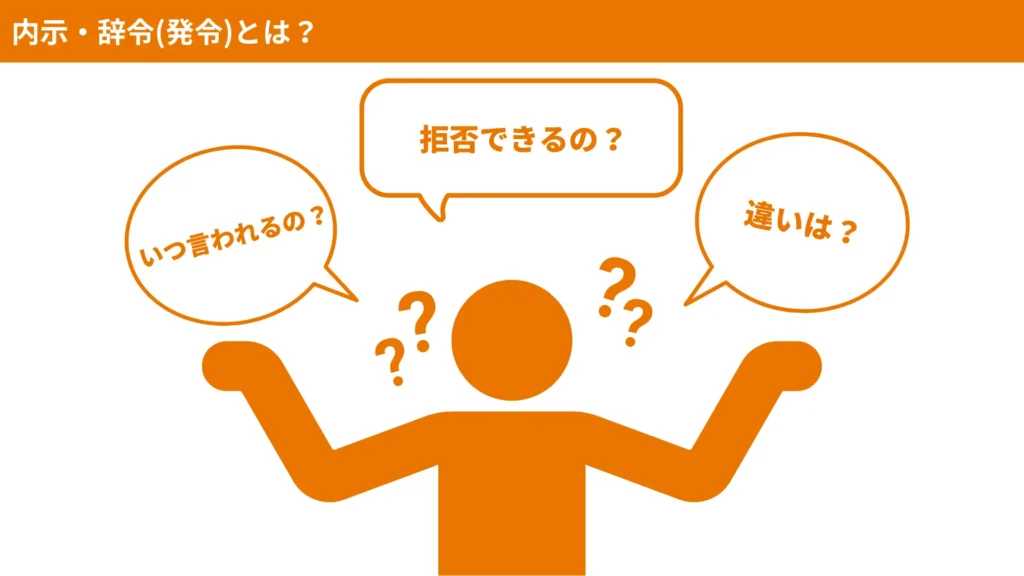
人事異動における「内示(ないじ)」とは、正式な辞令・発令の前に、従業員本人に異動の予定を事前に伝える非公式な通知のことです。
これはいわば“事前の予告”であり、従業員が新しい環境への準備を円滑に進められるよう配慮されたプロセスです。
内示の目的
- 異動対象者が業務の引き継ぎや生活の整理をするための準備期間を確保する
- 転勤を伴う場合は、住居の手配や家族の対応など現実的な調整時間を設ける
- チーム内のコミュニケーションや社内調整をスムーズに行うための準備段階
内示と辞令(発令)の違い
| 区分 | 内示 | 辞令(発令) |
|---|---|---|
| 形式 | 非公式(口頭・メールなど) | 公式な命令(書面で発行) |
| 法的拘束力 | 基本的になし | あり |
| タイミング | 通常1か月~1週間前 | 内示後に所定日に発令 |
内示はあくまで「予定を伝えるもの」であり法的拘束力はありませんが、企業内では慣習的に強い効力を持つことが多く、これをきっかけに準備が進んでいきます。
内示の注意点
- 正式発表前の情報であるため、社外や他部署に漏らさないことが重要
- 情報漏洩による社内混乱を避けるため、本人にも守秘義務が求められる
- 異動対象者には丁寧な説明や背景情報の共有が望ましい
内示・人事異動は拒否できる?
原則として拒否は難しい
内示は非公式な予告であっても、その後に発令される辞令には法的効力があります。
多くの企業の就業規則には「会社の業務命令として異動に従う義務」が定められており、正当な理由がなければ拒否はできません。
拒否が認められる可能性のあるケース
- 育児や介護など、個別事情への配慮が著しく欠けている場合
- 異動が不当な嫌がらせや報復的な配置転換に該当する場合
- 異動先の労働条件が著しく悪化する場合(賃金減、通勤困難など)
内示の段階でできること
- 上司や人事担当者に異動の理由や背景を確認する
- 自身の事情や困難について率直に伝え、配慮を求める
- 異動時期や配属先について調整の余地があるか相談する
内示は人事異動における重要な準備段階です。企業にとっては業務移行を円滑にするための手段であり、従業員にとっても新たな職務に向けた準備期間となります。
もし不安や問題点がある場合は、早い段階での対話を通じて、納得できる形で進めることが大切です。拒否ではなく、調整・相談の姿勢が現実的な対処法となります。
組織改編・人事異動が非効率になる本当の理由とは?
人事異動は「組織再編」や「人材育成」「事業強化」など、多くの目的に基づいて実施されます。しかし、実務では多くの企業が煩雑さやトラブル対応に追われているのが現実です。
その背景には、制度面のあいまいさや運用体制の不備といった根本的な原因が潜んでいます。
就業規則が整備されていない/運用されていない
人事異動に関しては、就業規則に明記することが基本です。
このような規定がなければ、企業が異動命令を出しても法的な根拠が不明確となり、従業員とのトラブルにつながる恐れがあります。
一方で、就業規則は存在していても、内容が古い・現場に周知されていないケースも多く、実務との乖離が生じています。
異動プロセスの属人化と情報の分散
人事異動は、対象者の選定、上司との調整、内示、承認、辞令発令、各部門への通知…と多くの工程を伴います。
この一連のプロセスがExcelや紙、メールで属人的に処理されていると、以下のような問題が発生します。
- 承認や連絡の遅延・漏れ
- 異動に伴うシステム設定(勤怠・給与・権限)の反映ミス
- 進捗の可視化ができず、関係者が混乱
特に複数の部署が関わる異動では、「誰が何をいつやるか」が不明確で、連携不足が非効率を生みます。
労働者への説明や配慮が不足している
就業規則に「業務上の必要がある場合、異動を命ずることができる」と記載されていても、それが一方的に押し付けられる形で運用されてしまうと、従業員の不満や抵抗につながります。
特に以下のような場合は、慎重な配慮が求められます。
- 育児や介護といった個別事情があるケース
- 異動先での待遇や通勤条件が大きく変わるケース
- 出向・転籍といった雇用形態が絡むケース
このような配慮が欠けた異動は、職場の信頼関係を損ない、生産性の低下にもつながります。
組織改編との連動性が設計されていない
組織改変(組織改正)と人事異動は密接に関係します。たとえば部門統合や新設に伴うポジション変更は、複数名の異動が同時に発生することになります。
しかし、これを一件ずつバラバラに処理していると、以下のような「組織設計上のズレ」が生まれます。
- ポジションのダブり・空白
- 管理ラインの不整合
- 異動連絡のタイミングがズレて、社内で混乱
一括で全体像を見渡し、調整・承認・発令までを連動して管理できる体制がなければ、複雑な組織改編はスムーズに進みません。
非効率の正体は「制度・運用・配慮不足」
人事異動や組織改変における非効率の根本原因は、以下の3点に集約されます。
制度の整備不十分(就業規則や異動ルールの不備)
運用の属人化と情報の分断
従業員への配慮や説明責任の不足
これらを解決するには、「制度の明確化」「業務フローの標準化」「関係者との情報共有」が欠かせません。
その実現手段として、ワークフローシステムの導入は極めて有効です。
人事異動・組織改編を効率化するには?

先述のように、人事異動や組織改変が非効率になる要因は「制度」「運用」「配慮不足」の3点です。これらを改善するには、以下の3つの視点から業務の見直しと仕組み化を行うことが重要です。
異動・改編のプロセスを“標準化”する
- 異動・組織改正の意思決定から承認、内示、辞令発令、システム反映までの全体フローを明文化
- 「誰が」「どのタイミングで」「何を」処理するかを明確にする
- 業務が属人化しないよう、テンプレート化・自動化可能な業務は仕組み化
関係者との情報共有を“可視化”する
- 経営層・人事・部門長・庶務・ITなど、複数部門が関与するため、進捗や承認状況をリアルタイムで共有する仕組みが必要
- 「内示済み」「承認待ち」「辞令発令準備中」などのステータス管理ができる仕組みを持つことで混乱を防止
- 引継ぎや人材配置の調整にも有効
配慮・通知・記録を“抜けなく”対応する
- 異動対象者の個別事情(育児・介護・健康状況など)を把握し、業務として配慮判断を記録に残す
- 内示のタイミングや辞令発令日など、重要な通知のタイミングを管理し、漏れなく連携
- 異動に伴う社内通知、関係システムへの自動連携も重要
ワークフローシステムで
人事異動・組織改編を「仕組み化」!
こうした業務の標準化・可視化・配慮判断を実現する手段として、ワークフローシステムの導入は非常に有効です。
ワークフローで解決できること
| 課題 | ワークフローでの解決策 |
|---|---|
| 異動手続きのバラつき | 業務フローをテンプレート化し、誰でも同じ手順で処理 |
| 承認の滞り・見落とし | システム上で承認ステータスを可視化・自動通知 |
| 情報共有の遅れ | 異動情報をリアルタイムに関係者と共有 |
| 個別配慮が抜ける | 異動フォームに配慮事項欄を設け、記録として残す |
| システム反映の手間 | 異動情報を人事・勤怠・給与・権限管理と連携 |
導入の効果
- 業務フローが「見える化」され、属人化を解消
- 異動ミス・遅延を防ぎ、スムーズな組織移行が可能に
- 記録と履歴が残り、監査・内部統制にも対応
- 労務トラブルのリスク低減にもつながる
人事異動や組織改変は、企業にとって日常的かつ戦略的な業務ですが、仕組み化されていない状態では手間・混乱・リスクを生み出す原因になります。
ワークフローシステムの導入によって、業務の可視化・標準化・省力化を実現することで、効率的でトラブルのない運用が可能になります。
FAQ・よくある質問
A. 人事異動は個々の従業員の勤務地や職務内容、役職などを変更することを指します。一方、組織改編(改正)は、部署の新設・統廃合・組織体制の見直しなど、企業全体の構造を変える取り組みです。
A. いいえ、内示はあくまで“予定”を本人に非公式に伝えるものであり、正式な命令ではありません。辞令(発令)が出されることで、初めて正式な異動が確定します。
A. 原則として、就業規則に異動命令に関する規定がある場合、正当な理由なく拒否することはできません。ただし、育児・介護・健康上の問題など正当な事情がある場合は、配慮が求められます。
A. はい、異動のルールや手続きは会社の就業規則によって異なります。ただし、厚生労働省が示すモデル就業規則や労働法の範囲内で定められている必要があります。
A. はい、業務プロセスを標準化し、関係者との情報共有を可視化することが重要です。その手段として、ワークフローシステムの導入が効果的です。
人事異動・組織改編の効率化にはジュガールがおすすめ!

ここまで見てきたように、人事異動や組織改編の現場では以下のような課題が繰り返されています。
- プロセスが属人的で、手続きや判断にバラつきがある
- 情報共有や承認の遅れで業務がストップする
- 従業員への説明・配慮が漏れやすく、トラブルにつながる
- 出向・転籍・役職変更など、複雑なパターンに柔軟に対応できない
これらを根本から解決し、スムーズでミスのない人事異動・組織改編を実現するなら、「ジュガール」のワークフロー機能が最適です。
ジュガールで解決できること
| 課題 | ジュガールでの解決 |
|---|---|
| フローが部署ごとにバラバラ | 自由にカスタマイズできる申請・承認ルートで、全社統一フローを実現 |
| 進捗管理ができない | ワークフロー画面でリアルタイムに承認状況を確認可能 |
| 内示・辞令の通知が遅れる | 通知の自動化・履歴の記録で、タイミングを逃さない |
| 配慮事項の確認が漏れる | 申請フォームにチェック項目やコメント欄を設定して確実にキャッチ |
| 関係者が多く、情報が錯綜 | 柔軟なステップ設計で、人事・総務・ITなど多部門をスマートに連携 |
ジュガールの強み
- ノーコードで簡単にワークフロー設計が可能
- 異動通知・辞令発令・システム反映までを一気通貫で管理
- 柔軟な承認ステップで、組織の複雑な構造にも対応
- 異動履歴を記録として残し、過去データの確認もスムーズ
- マルチ部門・多段階の承認プロセスにも無理なく対応
今こそ“業務改革”の第一歩をジュガールで
人事異動や組織改変は、企業の力を最大限に活かすための重要な経営手段です。
しかし、仕組みがなければ混乱とトラブルの温床にもなりかねません。
「ジュガール」なら、人事部門の負担を大幅に軽減し、正確でスピーディな異動業務の運用を実現できます。
- 業務プロセスの標準化
- 情報共有の可視化
- 配慮とスピードの両立
すべて、ジュガールで解決できます。
まずは、あなたの会社の“人事異動のやり方”を見直してみませんか?





