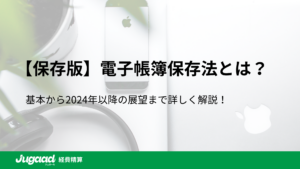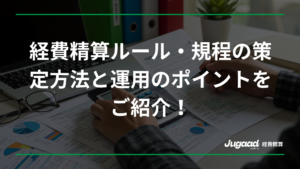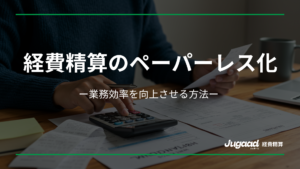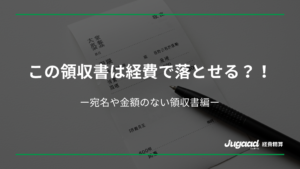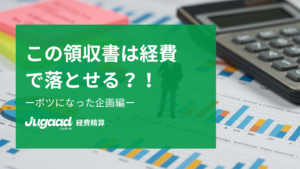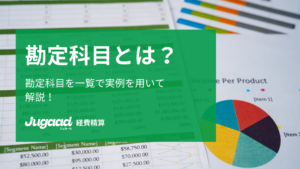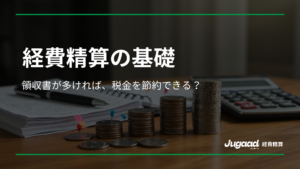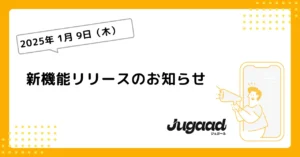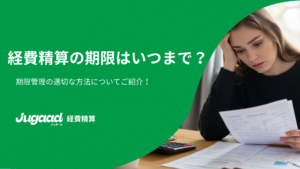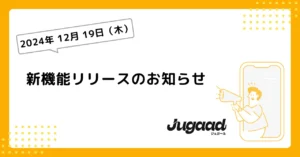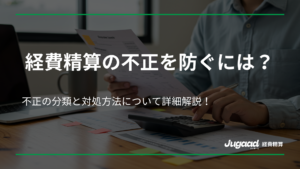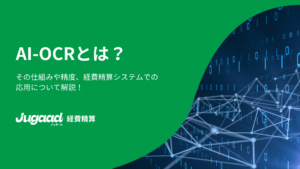この記事のポイント
- AI-OCRは高精度な読み取り技術だが、実務では読み取り“後”の業務設計が肝心。
- 経費精算業務には、人によるチェック、仕訳判断、法令対応など、AIだけで完結しない部分が多い。
- 自社に合った“ちょうどいい自動化”のためには、ワークフローや承認フローと一体化された仕組みが必要。
AI-OCRとは?従来のOCRとの違いと仕組みをわかりやすく解説
AI-OCRの基本的な仕組みと技術の進化
AI-OCR(エーアイ・オーシーアール)とは、「人工知能(AI)」を活用した文字認識技術のことで、紙の書類に印刷または手書きされた文字を、画像から読み取り、テキストデータに変換する技術です。
従来のOCRは、印刷された決まった形式の文書に対しては一定の精度で読み取りが可能でしたが、「フォーマットがバラバラな領収書」「スタンプが押されている請求書」「手書きの金額」などには対応が難しいという課題がありました。
そこで登場したのがAI-OCRです。
AI(人工知能)により、文書の構成や文字の形状を自動的に学習することで、非定型の帳票や、汚れ・かすれのある文字でも、柔軟に認識できるようになったのです。
たとえば、金額欄の文字の上にハンコが押されていたとしても、その下に書かれた文字の“パターン”をAIが推定し、正しい数字を読み取る、といったことが可能です。

OCRとの違い 手書き・非定型対応の有無
AI-OCRと従来のOCRの違いをひとことで言えば、「読み取れる範囲の広さと柔軟性」です。
従来型OCRは、フォーマットが固定された文書でなければ正確に読み取ることができませんでした。帳票に少しでもレイアウトの違いがあると、誤認識やエラーが頻発します。また、手書き文字には対応できないものがほとんどでした。
一方で、AI-OCRはレイアウトの違いを認識し、意味のある情報を抽出できるという特長があります。つまり、「どこに金額が書いてあるか」が帳票ごとに違っていても、AIがそれを“意味”で理解して抽出してくれるのです。
| 従来のOCR | AI-OCR | |
| 対応フォーマット | 固定レイアウトのみ | 非定型レイアウトにも対応 |
| 手書き文字 | 認識不可 | 認識可能(条件付き) |
| スタンプ・汚れへの対応 | 認識ミスが多い | AIが推定補完することが可能 |
| 精度向上の仕組み | 人のルール設定が必要 | 学習データにより自動的に改善 |
| 対象業務の広さ | 限定的(構造化文書) | 非構造化文書にも対応可 |
なぜ経費精算業務で注目されているのか
経費精算の現場では、営業活動や出張、接待などのたびに領収書が発生し、その内容を人が目で確認し、システムに手入力するという作業が発生しています。
この一連の流れは、非常に単純であるにもかかわらず、ミスが起きやすく、また膨大な手間がかかるため、経理部門の生産性を著しく下げる要因となっていました。
さらに、以下のような業務負荷もあります。
- 領収書の金額・日付・取引先の確認
- 社内ルールに基づいた科目の分類
- 仕訳の作成と会計システムへの登録
- 証憑の保存と検索(※電子帳簿保存法対応)
AI-OCRを活用することで、これらのプロセスのうち「読み取り」「入力」「一部の判定」までを自動化できます。
経理担当者が手を動かす場面は減り、確認や承認といった“判断”に集中できるようになるのです。
とくに、インボイス制度や電子帳簿保存法の影響で「紙の証憑を電子データとして正確に保存・管理する」ことが必須となっており、AI-OCRはその入り口として多くの企業で採用が進んでいます。

経費支払い業務の基本構造とAI活用の重要性
立替経費精算と支払依頼 業務内容の違いとそれぞれの課題
企業における経費支払い業務は、大きく分けて次の2つの方法があります。
立替経費精算:従業員が一時的に立て替えた経費を会社が後日払い戻す仕組み
支払依頼:請求書などに基づき、会社が取引先に対して直接支払う仕組み
一見すると「お金を払う」という点では同じに見えますが、実際の運用では支払相手・証憑(しょうひょう)・業務フロー・関係者など、さまざまな点で異なります。
| 立替経費精算 (従業員→会社) | 支払依頼 (会社→取引先) | |
| 証憑 | 領収書 | 請求書 |
| 返金方法 | 給与と合わせて精算 | 銀行振込などによる支払い |
| 担当部門 | 人事部門が主導 | 財務部門が主導 |
例えば、出張や営業活動で発生する交通費や宿泊費は、従業員が自身で支払い、後から精算する立替経費精算になります。一方、クラウドサービスの月額費用や備品購入費などは、会社が請求書に基づいて支払う「支払依頼」が一般的です。
それぞれの業務で使う書類も異なるため、AI-OCRを導入する際にも読み取るべき書式や注意点が異なってくるということを理解しておく必要があります。
業務ごとに異なる関係者(申請者、承認者、経理など)
経費の支払いには、1人の確認では済まないという特徴があります。特に経理業務では、「誰が、何の目的で、いくら使ったのか」を明確にし、それを複数の担当者がチェックする体制が一般的です。
【主な関係者と役割】
| 申請者 | 経費の支払いや立替返金を申請。 証憑とともに提出。 |
| 承認者 | 金額や内容が規程に適合しているかを確認・承認。 |
| 支払処理担当者 | 承認済の情報をもとに実際の支払い処理を実行。 |
| 経理担当者 | すべての処理を仕訳し、会計帳簿に反映。 |
このように、1件の経費でも複数の人が関与するため、属人化や入力ミスが積み重なるリスクが存在します。たとえば、申請内容の不備に気づかず支払が遅れたり、金額のミスで仕訳がずれてしまったりするケースです。
AIの活用によって、申請内容の自動補完、証憑との突合、異常検知などの作業を「人に代わって行うサポーター」として組み込むことが、ミスの防止や承認スピード向上につながります。

支払いはミスや不正が起きやすい ― 多重チェックの意味
お金が動く業務において、ミスや不正は企業の信頼や損益に直結する大きなリスクです。経費支払いの現場では、以下のようなトラブルが実際に発生しています。
- 金額ミス:数字の打ち間違いで多く支払ってしまう
- 二重支払:同じ請求書に対して複数回支払いが行われる
- 証憑不備:領収書が不鮮明で内容確認ができない
- 規程違反:本来必要な承認書類(稟議書など)が添付されていない
これらのリスクを抑えるため、企業では「多重チェック体制」を整えています。最低でも2人、場合によっては3人以上が確認することもあるため、どうしても手間や時間がかかってしまいます。
ここでAIが果たす役割は、人による確認の負荷を軽減し、見落としを防ぐことです。たとえば、
- 領収書の金額と入力内容が一致しているかを自動チェック
- 同じ画像・金額・取引先の申請がすでに存在しないかを検出(重複チェック)
- 承認済書類の添付漏れがないかをアラート
つまり、AIを使って「最初からミスの芽を摘む」ことで、業務の信頼性を高めつつ、スピードも保つという仕組みが構築できます。

AI-OCRで実現する業務の効率化と自動化の可能性
領収書・請求書からの情報抽出と仕訳補助
AI-OCRを活用することで、紙の領収書や請求書に記載された情報を自動で読み取り、経費精算業務や仕訳作業の一部を効率化できます。
特に、以下のような項目は人の手を介さずに抽出可能です。
- 領収書:日付、金額、取引先名、店舗名など
- 請求書:請求日、支払期日、請求金額、インボイス登録番号、振込先口座など
これにより、手入力による作業時間を大幅に削減し、ミスや抜け漏れのリスクも軽減されます。
ただし、AI-OCRが担えるのは、あくまで帳票から読み取れる情報の抽出まで。
経理処理に必要な勘定科目の判定や摘要の入力、最終的な仕訳の完成までには、補助的なロジックや確認が必要です。AI-OCRは「すばやく入力を代行してくれるサポーター」として位置づけるのが適切です。

勘定科目・消費税区分の自動補完
AI-OCRで抽出された情報をもとに、勘定科目や消費税区分を自動的に補完する補助機能も注目されています。
たとえば、
- 領収書に「タクシー代」と書かれていれば、「旅費交通費」が候補に上がる
- インボイス登録番号が付いていれば、10%課税かどうかを判定できる
ただし、これらの自動補完は「候補の提示」レベルであることが多く、確定には人の確認や他の業務データとの照合が必要です。
仕訳の完成には、次のような追加情報が求められます。
- 誰が使った経費なのか(申請者情報)
- どの部門・プロジェクトでの利用か(内部管理情報)
- どの稟議・予算に紐づいているか
- インボイス番号が正しいか(国税庁データベースと照合)
こうした社内・社外の情報をAIとITの力で補いながら、「仕訳の完成形」に近づけていくという姿勢が現実的です。

スマホやPCからの即時読み取り → データ反映までの流れ
AI-OCRの実力が発揮されるのは、証憑が発生したその場で即時に処理を開始できる点にあります。
【立替経費精算のシーン】
外出先での営業活動や出張中、レシートを受け取ったらすぐにスマホで撮影 → AI-OCRが即座に内容を読み取り、申請フォームに反映。そのまま申請・承認までスムーズに進められます。

【支払依頼のシーン】
オフィスでは複数の請求書をまとめてスキャン → AI-OCRが読み取って一覧化 → 支払期日・金額・取引先が自動で整備され、支払申請に即活用できます。
こうした即時反映により、“経理処理のスピード”と“データの正確性”の両立が実現可能になります。

AI-OCRは、経費処理や請求書管理において「文字を読み取ってくれるだけのツール」ではなく、「入力や分類の補助をしてくれる強力な支援ツール」です。
とはいえ、それだけですべてが完結するわけではありません。最終的な仕訳の完成には、人の判断や他システムとの連携も必要です。
AI-OCRの得意領域と限界を正しく理解したうえで、自社の業務プロセスにどう組み込むかを考えることが、自動化の第一歩となります。
読取精度はどのくらい信頼できる?AI-OCR精度の現実と限界
AI-OCRの読取精度は一般的に90〜95%前後
AI-OCRは、従来のOCRと比較してはるかに高い読取精度を実現していますが、それでも一般的な精度は約90〜95%程度とされています。
つまり、100個の項目を読み取ったときに、5〜10個は何らかの形で誤認識が起こる可能性がある、というのが現実的な数字です。
【読取精度を左右する要因】
| 帳票のレイアウトの複雑さ | 非定型であればあるほど、精度は下がる可能性 |
| 手書き文字の有無 | 機械学習が未学習の文字形は認識ミスが起きやすい |
| スキャン画像の質 | 傾き・ぼやけ・縮小画像は誤認識の原因に |
| 使用するAIエンジン | 製品ごとに精度は異なる(独自AI、Google Vision、Tegakiなど) |
また、AI-OCRの精度は日々進化しており、学習データが増えるほど正確性が向上する特性がありますが、「常に100%正確」という状態には達していないことを前提に活用する必要があります。
スタンプ重ね・かすれ文字・手書き崩れがエラー要因
AI-OCRの精度を下げる大きな要因のひとつが、帳票に含まれる“ノイズ”です。
以下のようなケースでは、AIでも正確に読み取ることが難しくなります。
- 領収書に押されたスタンプが文字の上に重なっている
- 印字が薄れていたり、プリンタのかすれで一部の文字が読めない
- 手書きの文字が独特の癖字や誤字になっている
- 項目名がレイアウト上の制約で変則的な位置にある
たとえば「3,000円」が「3.000円」と見えるような微妙な誤認識や、「2023年」の「3」が「8」に見えるようなケースなどは、いずれも業務上の金額ミス・誤仕訳に直結する可能性があるため、実務では慎重な対応が求められます。

「仕訳精度100%=読取精度99.9%以上が必要」ではない理由
経理業務においては「ミスが許されない」ため、つい“100%の読み取り精度”を求めたくなる心理があります。
しかし実際の現場では、仕訳の精度を高く保つことと、AI-OCRの読取精度はイコールではありません。
なぜなら、
- AI-OCRで読み取れない項目は、他の手段で補える(たとえば手入力、予算データ、自動補完ルール)
- 自動補完やチェック機能でミスを防ぐフローがある(承認フロー、アラート機能など)
- AIが読み取りミスを起こしやすい項目は、必ず人が見る設計にできる
つまり、AI-OCRは“完全自動化”のための道具ではなく、“正確性とスピードを両立するための補助ツール”と捉えるのが最も現実的です。
AI-OCRとアウトソーシングの違いとは?
アウトソーシング型は「入力代行」。すべてが自動化されるわけではない
経費精算や請求書処理において、オペレーターが帳票画像を目視確認し、入力作業を代行する「アウトソーシング型サービス」は、一定の需要があります。
特に非定型なフォーマットや、手書き・スタンプ重ねなどがある帳票にも柔軟に対応できることから、読み取り精度の高さが期待される手段のひとつです。
しかし、ここで注意すべきは、オペレーターの業務範囲はあくまで「項目の入力代行」に留まることが多いという点です。
たとえば、以下のような付加情報の判断・登録については、サービスによって対応が異なります。
| 項目 | 実際の入力可否(サービスによる) |
| 勘定科目の付与 | △ 手作業で登録が必要な場合も多い |
| 部門コードの設定 | △ 社内情報と連携されていなければ不可 |
| プロジェクトのひもづけ | × 多くのサービスでは対応外 |
| 仕訳日・摘要の補完 | △ 汎用処理でしか対応できないことがある |
つまり、「読み取り精度は高いが、その後の業務フローは自社で行う必要がある」という現実を見落とさないことが大切です。
アウトソーシング型であっても、請求書や領収書の処理が“完全に完結する”わけではないという前提で、検討する必要があります。

AI-OCRは即時処理だが完全自動ではない
AI-OCRは、帳票をスキャンまたはスマートフォンで撮影するだけで、日付・金額・取引先名などの情報を瞬時に読み取り、申請画面に反映することができる技術です。
読み取りにかかる時間は数秒〜十数秒。
まさに、リアルタイムでの処理が求められる経費精算にフィットするツールです。
ただし、AI-OCRも万能ではなく、以下のような特徴と限界を持ちます。
【AI-OCRの特長】
| スピード | ◎ 即時反映が可能(秒単位) |
| 精度 | ◯ 読み取り精度は90〜95%が一般的。完璧ではない |
| 補完範囲 | △ 勘定科目・税区分は候補提示レベルが多い |
| 柔軟性 | ◎ ユーザーがすぐに修正・再申請できる |
ここで重要なのは、「精度が不完全でも、確認・修正できるフローを組むことで業務としては成立する」ということです。
特に以下のようなサポート機能があるAI-OCR搭載システムでは、現場での安心感も高まります。
- 読み取り精度のスコア表示(例:店舗名:85%)→「ここは注意して確認しよう」とわかる
- 読み取り内容と証憑画像の並列表示 → 一目で突合可能
- 自社ルール(例:旅費は常に交通費)を反映した補完ロジック
比較表で見る、選び方の要点と注意点
| AI-OCR | アウトソーシング | |
| 処理スピード | ◎ 即時反映 | △ 数分〜数十分 |
| 精度 | ◯ 90〜95%前後(要補完) | ◎ 高精度(手入力) |
| コスト | ◎ 定額/従量制が多く低価格帯 | △ 件数が増えるとコスト上昇 |
| 自動化の範囲 | ◯ 連携設計次第で高い | △ 入力止まりが多い |
| 柔軟性・修正のしやすさ | ◎ ユーザー即時操作可 | △ 修正対応にタイムラグあり |
| 向いているケース | ・即時処理が求められる業務 ・承認フローがある中堅〜大手 | ・正確性最優先 ・特殊帳票が多い業務 |
AI-OCRもアウトソーシングも、“読み取るだけ”ならどちらも有効です。
ただし、経費精算における本質的な効率化は、「誰がどの情報をどこまで処理してくれるのか?」を正確に把握することにあります。
請求書処理におけるAI-OCRの実力とは?
インボイス登録番号の自動抽出と登録事業者の判定補助
インボイス制度が始まり、請求書処理において「適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)」を確認することが、企業にとって欠かせない業務になりました。
これを目視で毎回確認するのは非常に手間がかかり、人為的ミスや確認漏れも起きやすくなります。
AI-OCRを活用すれば、請求書に記載されたインボイス登録番号を自動で読み取り、国税庁のデータベースと照合して「登録済事業者かどうか」を即時判定できます。
これにより、以下のような実務的メリットが得られます。
- 登録番号が未記載・不正確・形式不備な請求書を自動検出
- 国税庁登録データと突合し、適格請求書でないものを自動でアラート
- 税務調査時にも対応しやすい、正確な取引記録の蓄積

振込先口座・支払期日・提供期間などの正確な読み取り
請求書に記載されているのは金額だけではありません。
振込先口座情報、支払期日、サービス提供期間なども、経理処理において非常に重要です。これらの情報が正確でないと、支払遅延や誤送金といった問題につながりかねません。
AI-OCRは、こうした情報も画像から自動で抽出することができます。
| 抽出対象 | 活用例 |
| 振込先口座情報 | 銀行名・支店名・口座番号・名義人の確認、誤送金防止 |
| 支払期日 | 支払遅延・早払いの抑止、キャッシュフロー管理の正確性向上 |
| 提供期間 | サービス期間の確認、前払/後払の処理判断、税務対応などに使用 |
読み取ったこれらの項目は、自動的に支払申請フォームに反映されるため、経理担当者がわざわざ入力・転記する必要がなくなり、ミスのない迅速な処理が実現します。
重複申請の自動検知と、電子証憑特有のリスク防止
請求書・領収書を電子化することで生まれるメリットは大きい一方で、新たなリスクも発生します。
そのひとつが「重複申請」です。
紙証憑のときは、証憑を一度提出すると証憑は物理的に手元からなくなります。そのため、同じ書類を複数回提出することは基本的に起こりません。
しかし電子証憑の場合は、ファイルを提出しても、データは手元に残ります。そのため、「うっかり再申請してしまう」ことが起きやすくなります。さらには、意図的な不正申請の温床にもなり得ます。
ここでAI-OCRは、「画像の構成」「金額」「日付」「取引先情報」などを複合的に照合して、「この証憑は以前にも申請されています」と自動検知してアラートを発出することが可能です。
これにより、以下のようなリスクを防ぐことができます。
- 同じ領収書や請求書を誤って二重申請してしまうヒューマンエラー
- 意図的に同じ証憑を再利用する不正申請
- 同一内容の支払処理・仕訳が二重で行われることによる経理上のミス
【AI-OCRは読み取りだけでなく、“実務の安心”も支える】
AI-OCRは、請求書の文字情報を高速かつ正確に読み取るだけでなく、インボイス制度対応、振込ミス防止、重複申請の回避など、実務に直結する業務リスクの防止機能も併せ持つツールへと進化しています。
とくに電子証憑の普及により、業務のスピードは上がる一方で、「提出したつもり」「別の人が処理したと思っていた」といったデジタル特有のミスや見落としが起きやすくなっているのも事実です。
こうした時代背景において、AI-OCRは、「人が気づけなかった問題」を事前に知らせてくれるアシスタントのような存在として、経理・財務業務を支えています。
セキュリティと電子帳簿保存法(電帳法)対応
AI-OCRを使うということは、「会社のお金に関わる情報」を読み取り、クラウドに保存するということです。
そのため、情報の安全性(セキュリティ)と、法律に合っているか(法令対応)はしっかり確認しましょう。
【セキュリティで見るべきポイント】
- 通信が暗号化されているか(たとえばSSL通信:データを盗み見られない仕組み)
- データは日本国内のサーバーに保管されているか
- 管理者だけがアクセスできる仕組みがあるか(パスワード制限など)
【電帳法対応とは?】
電子帳簿保存法(電帳法)という法律により、「電子化した領収書は一定の条件を満たして保存すること」が必要です。
たとえば、
- 書類の保存にタイムスタンプ(改ざん防止の印)が付く
- 検索できるようになっている
- 記録の改ざんがされていないと証明できる仕組み
これらの要件を満たしていることを証明するのが、「JIIMA認証(ジーマにんしょう)」という制度です。
これは公的な第三者機関が「このシステムは法律に合っていますよ」とお墨付きを与える仕組みです。
対応-1024x572.webp)
導入ツールを選ぶときの判断基準とは?
AI-OCRをはじめとする経費精算ツールには、「人が入力するアウトソーシング型」「AIで読み取る自動化型」「その両方を組み合わせたハイブリッド型」など、さまざまな方式があります。
第5章ではそれぞれの違い(精度・スピード・費用など)を比較しましたが、ここでは「どれが自社に合っているか」を判断する視点に絞って解説します。
自社の業務量・スピード感・確認体制を見直そう
AI-OCRが向いているのか?アウトソーシングが合っているのか?を考えるうえで、まずは自社の業務の「ボリューム」と「進め方」に目を向けましょう。
【自社の実情に照らしてみよう(判断軸の例)】
| 課題 | おすすめのタイプ |
| 毎月の領収書・請求書がとても多い | → AI-OCR搭載型(大量処理に強い) |
| とにかくスピードを重視したい | → AI-OCR搭載型(即時反映) |
| 経費の種類やフォーマットがバラバラで判断が難しい | → ハイブリッド型(AI+人の補完) |
| 社内にチェック担当が少ない/属人化している | → アウトソーシング型またはハイブリッド型 |
| 承認フローやルールが整っている | → AI-OCR搭載型(制度で補完できる) |
AI-OCRで経費精算業務はどこまで自動化できるか?
AI-OCRは「経費精算の自動化」の入口
AI-OCRは、手入力が当たり前だった経費処理の世界において、読み取り作業の自動化という“最初の大きな一歩”を実現する技術です。
- 領収書や請求書から金額・日付・取引先を即座に読み取る
- スマホで撮影すれば、そのまま申請フォームに反映される
- インボイス番号の確認や、重複申請の検知まで自動でできる
ここまでできれば、かつて時間と労力をかけていた「入力・確認・申請」の多くが短縮され、業務スピードは格段に向上します。
「全部自動にしよう」としなくても大丈夫
AI-OCRを検討するとき、「精度が100%じゃないと使えないのでは?」と思う方もいます。
しかし実際には、AIが8〜9割の作業をこなし、人がチェックする体制があれば、十分に実用的で、しかも安心感があるということが、今回の記事を通じて伝わったのではないでしょうか。
完璧を目指すより、「人がやるべきことと、AIに任せられることを分けて考える」という視点が、これからの経費精算では重要です。
| AI-OCRが得意なこと | まだ人の判断が必要なこと |
| 領収書・請求書の情報の読み取り | 勘定科目の最終決定(曖昧なケース) |
| インボイス番号の抽出と照合 | 例外的な処理や不明点の解釈 |
| 重複申請の自動検出 | 不正の意図や文脈の判断 |
よくある質問(FAQ)
A. 従来のOCRは「決まったレイアウトの印字文書」に強く、少しでもフォーマットが変わると精度が落ちやすいという弱点がありました。AI-OCRはAIがレイアウトや文字のパターンを学習することで、手書き・スタンプ重なり・かすれなどを含む“非定型帳票”にも柔軟に対応できる点が大きな違いです。
A. 一般的には90〜95%前後が目安とされており、従来のOCRより高精度です。ただし、スタンプ重なり・かすれ・癖の強い手書きなどがあると誤認識が発生するため、「AIが一次入力を行い、人が最終確認する」前提で設計するのが現実的です。
A. AI-OCRで自動化できるのは、領収書や請求書からの「日付・金額・取引先名・インボイス番号」などの読取と入力の部分です。最終的な勘定科目の決定や、例外的な処理の判断、不正の有無などは、社内ルールや人の確認と組み合わせて運用する必要があります。
A. 両方で活用できます。立替経費では、スマホで領収書を撮影すると、その場でAI-OCRが読み取り、経費申請画面に自動反映できます。請求書支払依頼では、まとめてスキャンした請求書から支払期日や振込先を一覧化し、支払処理までの流れを効率化できます。
A. AI-OCRは請求書に記載されたインボイス登録番号を自動抽出し、登録番号の形式チェックや登録事業者かどうかの判定補助に使えます。また、電子帳簿保存法に対応したシステムと組み合わせることで、証憑画像の保存要件(改ざん防止・検索性など)を満たしながら、ペーパーレスでの保管が可能になります。
A. 電子データはコピーしやすい一方で、AI-OCRとシステム側の機能を組み合わせることで「同じ画像・金額・日付・取引先の申請」を自動検知し、重複申請にアラートを出すことができます。これにより、うっかりミスだけでなく、意図的な再申請の抑止にもつながります。
A. ジュガールでは、AI-OCRで読み取った金額・日付・取引先情報をもとに、勘定科目や消費税区分の自動補完、インボイス番号のチェック、重複申請の検知などまでカバーできます。読み取りだけで終わらず、その先の仕訳・会計連携・電帳法対応まで一気通貫でつなげられる点が特徴です。
ジュガール経費精算なら、読み取りの先まで自動化できる

AI-OCRによる読み取りにとどまらず、「その後の仕訳処理や会計連携までつなげたい」という方には、ジュガール経費精算という選択肢もあります。
- AI-OCRで読み取ったデータをもとに、勘定科目や消費税区分を自動補完
- 重複チェック・インボイス照合も自動対応
- 会計システムとの連携まで可能な、“業務全体を見据えた自動化”に対応
ぜひご検討ください。