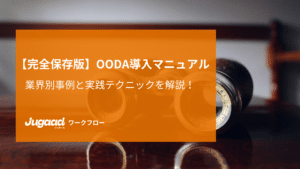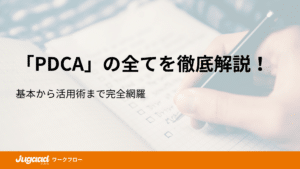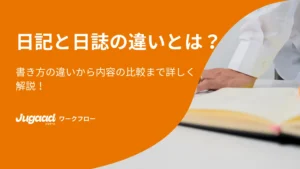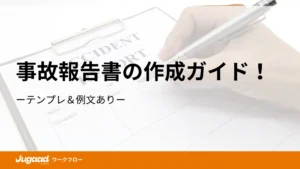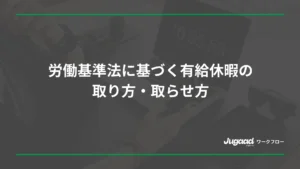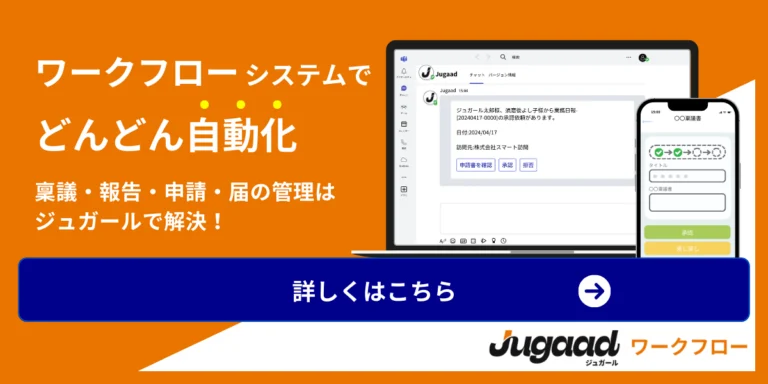クラウド型ワークフローシステムとは?
業務の効率化、リモートワークへの対応、コスト削減——こうした課題に直面している多くの企業にとって、ワークフローシステムのクラウド化は、もはや“選択肢のひとつ”ではなく“有力な手段”として注目されています。
クラウド型ワークフローシステムとは、社内の稟議書や申請書などの承認プロセスを、インターネット経由で運用・管理するための仕組みです。ユーザーは社内ネットワークに縛られることなく、パソコンやスマートフォン、タブレットからいつでもどこでもアクセスし、申請・承認などの業務を進めることができます。
なぜ今、クラウド型が選ばれているのか
従来は、自社内にサーバーを構築して運用する「オンプレミス型」が一般的でしたが、昨今はクラウド型の利用が加速しています。その理由は明確で、導入や運用が手軽でありながら、スピーディーな業務遂行を支える柔軟性があるためです。
特に、テレワークやハイブリッドワークが一般化する中で、場所にとらわれずに業務を遂行できる環境は大きな強みとなります。クラウド型ワークフローは、こうした新しい働き方を支えながら、業務全体の可視化やスピードアップにも貢献しています。
多くは「SaaS型」という形式で提供される
クラウド型ワークフローシステムの多くは、「SaaS(サース)」と呼ばれるスタイルで提供されています。
これは「Software as a Service(サービスとしてのソフトウェア)」の略で、ソフトウェアを購入・インストールするのではなく、必要な機能をインターネット経由で利用できるサービス形式のことです。
ユーザーはブラウザからすぐに利用を始めることができ、システムの保守やアップデートはすべてサービス提供者が対応します。
そのため、IT部門の負担を大きく減らしながら、常に最新の状態で業務を進められるのも大きなメリットです。
ワークフローシステムの種類(クラウド型とオンプレミス型)
ワークフローシステムとは、社内の申請や承認、報告といった一連の業務フローを、システム上でスムーズに処理するための仕組みです。
このシステムには主に「クラウド型」と「オンプレミス型」という2つの提供形態があります。
それぞれの違いや特徴を理解することで、自社にとってどちらがより適しているのかを見極めることができます。
ここでは両者をわかりやすく比較しながら、それぞれのメリット・留意点を丁寧に解説していきます。
オンプレミス型とは?
オンプレミス型とは、ワークフローシステムを自社内のサーバーやネットワークに構築して運用する形態のことです。
言い換えると、「システムを自社で持ち、運営・管理も自分たちで行う」というスタイルです。
大きな特長は、自社の業務に合わせてシステムを細かくカスタマイズできること。
また、データやアクセスの管理をすべて自社で行えるため、セキュリティの自由度が高く、金融業や医療業など厳格な管理が求められる分野では今も選ばれることがあります。
ただし、サーバーやソフトの導入にかかる初期費用が高額になりがちで、社内にITインフラの知識を持った担当者が必要というハードルもあります。
導入後の保守やアップデート、障害対応もすべて社内で対応しなければならず、中小企業には負担が大きい選択肢といえるでしょう。
クラウド型とは?
クラウド型とは、インターネット経由でワークフローシステムを利用する形態で、ソフトウェアやサーバーを自社で持つ必要がない仕組みです。
システムはサービス提供会社(ベンダー)がクラウド上で運用・管理しており、利用者はブラウザなどからログインして使います。
最大の特長は、インフラの準備が不要で、スピーディーに導入できる点です。
自社でサーバーを設置したり、専門的な知識が必要だったりすることがないため、初めてシステムを導入する企業でも始めやすいのが魅力です。
また、複数拠点からのアクセスや、テレワーク・出張中の対応も可能。PC・スマートフォン・タブレットなど、端末を問わず利用できる柔軟性も強みです。
アップデートやセキュリティ対策も提供元が行うため、常に最新の機能を安心して利用できるというメリットがあります。
一方で、ベンダー側の仕様に依存する部分があるため、自由なカスタマイズや独自機能の追加には限界がある点も理解しておく必要があります。
クラウド型とオンプレミス型の主な違い
ここまでで、クラウド型とオンプレミス型それぞれの特長について紹介してきました。
では、実際にどちらを選ぶべきかを考える際、どのような違いに着目すればよいのでしょうか。
ここでは、インフラ管理、費用、拡張性、運用負荷、セキュリティ対応など、実務に直結する主要な観点で両者を比較してみましょう。
導入のしやすさや業務の柔軟性を重視する場合はクラウド型、カスタマイズ性や自社管理の徹底を重視する場合はオンプレミス型といった選び方が見えてくるはずです。
特に最近では、クラウド型の導入が増えている理由が、この比較からも明確に読み取れるようになります。
| 項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |
| インフラ管理 | 不要(提供事業者が対応) | 必要(自社で構築・保守) |
| 初期費用 | 低コスト/無料が多い | 高額(サーバー・ライセンス等) |
| 拡張性・柔軟性 | 高い(すぐに機能追加可能) | 低め(拡張には追加構築が必要) |
| アップデート | 自動で適用 | 自社で手動対応 |
| セキュリティ設定の自由度 | 標準対応(サービス側に準拠) | カスタマイズ性が高い |
| 運用負荷 | 軽い(ベンダーに任せられる) | 重い(IT部門の対応が必須) |
| 遠隔アクセス | 可能(インターネット経由) | 制限あり(社内ネットワーク前提) |
どちらが優れている、というよりは「どちらが自社に合っているか」が重要です。
次章では、こうした違いを踏まえたうえで、オンプレミス型からクラウド型へ移行する際に注意すべきポイントを解説していきます。
オンプレミスからクラウド型へ移行する際の注意点
オンプレミスからクラウド型ワークフローへ移行する際は、現行の業務フローの整理、データ移行・システム連携の整備、セキュリティやコンプライアンス要件の確認が重要です。
これらを事前に押さえておくことで、スムーズで安全な移行が実現できます。
近年、多くの企業がオンプレミス型からクラウド型への移行を進めています。
しかし、単純に「クラウドのほうが便利そうだから」という理由だけで切り替えてしまうと、思わぬトラブルや業務の混乱を招くこともあります。
ここでは、オンプレミスからクラウドへ移行する際に事前に把握・検討すべき主なポイントを紹介します。
円滑な移行を実現するためには、単なる機能比較ではなく、運用・組織・データに関する視点も重要です。
現行システムの整理と業務フローの見直し
まず最初に行うべきなのは、現在使っているオンプレミス型ワークフローシステムの機能や運用状況を正確に把握することです。
どの部署がどのような申請フローを使っているのか、どのようなカスタマイズが施されているのかなど、業務フローを可視化することが第一歩となります。
クラウド型に切り替える際、すべての機能が同じように再現できるとは限りません。
特に、複雑な承認ルールや既存システムとの独自連携がある場合、それをクラウド上でどう実現するかを検討する必要があります。
この段階を丁寧に行うことで、移行後のギャップを最小限に抑え、業務の混乱を防ぐことができます。
データ移行と連携の整備
オンプレミスで運用していたワークフローシステムには、過去の申請データや添付ファイル、履歴情報など、業務にとって欠かせない情報が蓄積されています。
クラウド型に移行する際には、これらのデータをどこまで移行するのか、どのような形式で持っていくのかを明確にする必要があります。
また、ワークフローと連携している他の業務システム(人事・会計・ファイル管理など)との連携仕様や方式の確認も重要です。
クラウド型ではAPIを利用した連携が主流となるため、既存システム側での対応状況や開発の必要性など、システム間の整合性を事前に検討しておく必要があります。
セキュリティとコンプライアンスの確認
クラウドへの移行で最も多く聞かれる懸念のひとつが、「本当にセキュリティは大丈夫か?」という点です。
クラウド事業者は高水準のセキュリティ対策を講じているケースが多いものの、それが自社の運用ポリシーや業界ガイドラインに適合しているかは個別に検証する必要があります。
特に、個人情報や機密情報を取り扱う場合には、データの保存場所(国内/海外)、暗号化の有無、アクセス権限の設計、操作ログの取得・保存といった要素をチェックしておくことが大切です。
あわせて、クラウド事業者がISO 27001やISMSなどの国際的な情報セキュリティ基準に準拠しているかどうかも、信頼性を見極める材料になります。
クラウド型ワークフローのメリット

クラウド型ワークフローには、導入のしやすさ、柔軟な働き方への対応、運用負荷の軽減、他システムとの連携性といった多くの実用的なメリットがあります。
これらの特長が、今や企業規模を問わずクラウド型が選ばれる理由の一つとなっています。
ワークフローのクラウド化は単なるITツールの入れ替えではなく、業務効率の改善や働き方の進化を支える“仕組みの変革”につながります。ここでは、代表的なメリットをより詳しく見ていきましょう。
導入が手軽でスピーディー
クラウド型は、サービス提供者があらかじめインフラやソフトウェア環境を構築しているため、ユーザー側ではサーバーの準備やソフトのインストールといった複雑な作業が不要です。申込みを済ませれば、すぐに利用を開始できるケースが多く、システム導入にありがちな「立ち上がりの遅さ」がありません。さらに初期費用も抑えられることが多いため、まずは一部部門で試験導入し、徐々に全社展開するような柔軟な導入計画も立てやすいのが特長です。IT部門の負荷が少なく、運用のスタートをスムーズに切れることは、クラウド型最大の利点のひとつといえます。
どこからでもアクセスでき、柔軟な働き方に対応
クラウド型ワークフローは、インターネット接続さえあれば場所を選ばずアクセスできるため、在宅勤務や出張先、外出中のカフェからでも申請や承認が可能になります。これにより、従来のように上長の帰社を待って承認が滞るといった問題を回避し、意思決定のスピードを飛躍的に高めることができます。また、多くのクラウド型製品はスマートフォンやタブレットにも対応しており、操作性に配慮された画面設計がされています。こうした利便性は、営業部門や現場職のスタッフなど、従来紙や口頭で処理していた業務をデジタル化する上でも非常に効果的です。
常に最新の機能が使える
クラウド型サービスでは、ベンダー側で機能のアップデートやセキュリティ対応が行われ、それが自動的に利用者の環境にも反映されます。これにより、ユーザーは常に最新の状態でシステムを使い続けることができ、社内でアップデート作業やバージョン管理を行う必要がありません。制度改正や社会的な要請へのスピーディーな対応、UI/UXの改善、新しい業務ニーズへの機能追加など、変化に強い仕組みが自然と維持される点は、運用の手間とリスクを大きく軽減します。また、こうした改善が継続的に行われることで、長期的に価値あるツールとして定着しやすいのもメリットです。
他システムとの連携がしやすい
多くのクラウド型ワークフローは、他のクラウドサービスや社内システムとの連携を前提とした構成になっており、APIやWebhookを利用することでさまざまなツールと柔軟に接続することができます。例えば、申請データをそのまま会計システムに連携したり、人事マスタと自動連携して承認ルートを制御したりといった運用が可能になります。これにより、業務プロセスの効率化だけでなく、データの一元化やヒューマンエラーの防止にもつながります。クラウドを活用した業務の“横串化”が容易になり、DXの基盤としても大きな価値を発揮します。
クラウド型ワークフローの課題(デメリット)
クラウド型ワークフローは多くの利点を持ちますが、同時にカスタマイズの制限、インターネット依存、セキュリティ・コンプライアンス対応といった注意点も存在します。
導入前にこれらの課題を正しく理解しておくことが、スムーズな運用と後悔しない選定につながります。
便利さや柔軟性の高さが魅力のクラウド型ですが、すべての企業・業務にとって万能というわけではありません。クラウドならではの制約や、業種・組織によっては致命的な要素になり得る部分もあります。ここでは、代表的な3つの課題について詳しく解説します。
カスタマイズの自由度に制限がある
クラウド型は多くの企業に共通して使いやすいように標準化されているため、オンプレミス型のように個別仕様にあわせた柔軟なカスタマイズは難しい場合があります。特に、承認フローに特殊な条件がある、業務プロセスに細かいルールがある、といった場合には、既存機能では対応できない可能性があります。また、独自の帳票レイアウトや特殊な通知ルールなどを導入したい場合も、ベンダーに問い合わせが必要だったり、追加開発が必要になったりすることがあります。導入前には、自社が求める要件がクラウド型でどこまで実現できるかを十分に検討することが重要です。
インターネット環境への依存
クラウド型の運用にはインターネット接続が不可欠であり、ネットワークトラブルや回線の制限が発生すると業務が停止するリスクがあります。社内LAN上で完結していたオンプレミス型とは異なり、すべてのやりとりが外部回線に依存するため、通信品質やセキュリティポリシーに課題がある場合は導入前にしっかりと確認しておく必要があります。とくに建設現場や製造業など、安定したインターネット接続が確保しづらい業務環境では慎重な検討が求められます。また、オフライン環境での作業が必要な業務には適さないケースもあります。
セキュリティやコンプライアンスへの不安
クラウド型のセキュリティ対策は年々進化していますが、利用企業側としてはデータの保存先や取り扱いルールを正確に把握し、自社の情報セキュリティポリシーと照らし合わせることが不可欠です。たとえば、個人情報や機密情報をクラウドに保管する際には、データセンターの所在地(国内/国外)、通信の暗号化、アクセス制御の仕組み、監査ログの有無などを確認する必要があります。医療・金融・公共といった業界では、法令や業界ガイドラインへの準拠も求められるため、ベンダーが取得しているセキュリティ認証(ISO 27001、SOC 2など)も比較検討のポイントになります。
ワークフローをクラウド化する手順

ワークフローのクラウド化は、現状分析から導入・定着まで段階的に進めることで、業務への影響を最小限に抑えながらスムーズに導入できます。
やみくもに切り替えるのではなく、明確なステップを踏んで進めることが成功の鍵です。
クラウド型ワークフローシステムの導入には、いくつかのフェーズがあります。
どの段階で何を検討すべきかを把握しておくことで、導入後のトラブルや想定外のコスト発生を防ぎ、運用までをスムーズに進めることができます。
ここでは、一般的な導入プロセスを6つのステップに分けて解説します。
1. 現状の調査と課題の洗い出し
導入の第一歩は、現状の業務フローとシステム環境を正しく把握することです。
どの部署でどのような申請・承認の流れが使われているのか、どのツールが利用されているのか、そしてどこに課題や非効率が存在しているのかを明確にします。
紙やメールによる申請が残っている場合、それらをどう置き換えるのかも検討が必要です。
属人的な運用や例外処理が多い場合は、標準化できる余地も見つかるでしょう。
現状を可視化することで、クラウド導入による改善効果を予測しやすくなります。
このステップは、後工程の要件定義にも直結する非常に重要なプロセスです。
2. 目的設定と要件定義
クラウド化の目的を明確にすることは、成功への道筋を描くうえで欠かせません。
「承認のスピードを上げたい」「外出先からでも申請処理をしたい」など、現場のニーズに基づいた目的を設定しましょう。
その上で、実現のために必要な機能や条件を洗い出し、「必須機能」「あれば便利な機能」「不要な機能」に分類します。
たとえば多段階の承認フロー、差し戻しルール、グループ管理、通知設定、外部システム連携などが検討項目になります。
要件定義が曖昧だと、導入後の「想定と違った」というミスマッチを招きかねません。
目的と要件を文書化しておくことは、社内調整やベンダー選定の場でも役立ちます。
3. システム選定と比較検討
要件が固まったら、具体的なクラウド型ワークフローシステムの候補を探し、比較検討します。
このとき重視すべきポイントは多岐にわたります。UIの使いやすさ、価格帯、他システムとの連携性、サポート体制、カスタマイズの柔軟性、セキュリティレベルなど、総合的な観点で判断しましょう。
トライアル利用ができるサービスは積極的に試し、実際の操作感を現場メンバーにも確認してもらうと安心です。
導入後の拡張性や運用コストも含めて評価することで、長期的に使い続けられるサービスを選べます。
選定段階では、価格だけで決めないことが成功のポイントです。
4. パイロット導入とフィードバック
本格導入の前に、特定の部門やチームでパイロット運用(試験導入)を実施することが重要です。
この段階では、実際の業務フローに沿って操作しながら、設定や画面構成、通知のタイミングなどを検証します。
利用者からのフィードバックを集めることで、操作に迷うポイントや説明不足の部分が明らかになります。
その結果をもとにマニュアルの改善や設定の見直しを行えば、全社導入時の混乱を減らすことができます。
また、パイロットチームが先行ユーザーとして社内の推進役になることで、導入全体の定着率も高まります。
5. 本格導入とカスタマイズ
パイロットでの検証が終わったら、いよいよ全社導入へと移行します。
この際には、ユーザー権限の設計や申請カテゴリごとの承認ルート、通知方法など、組織に合わせたカスタマイズを丁寧に行うことが求められます。
クラウド型は初期設定が手軽な反面、柔軟性が高いため、設計次第でユーザーの使いやすさが大きく左右されます。
できるだけ複雑になりすぎない設計と、運用後の変更にも対応しやすい構成にしておくとよいでしょう。
必要に応じてベンダーと相談しながら、スムーズに本番環境へ移行できるように準備します。
6. トレーニングと定着支援
導入が完了しても、それで終わりではありません。
現場の利用者が迷わず使えるように、トレーニングや操作マニュアルの整備を徹底しましょう。
初期段階では「誰に聞けばいいのか」「どう設定すればいいのか」がわからず、現場が戸惑うことも少なくありません。
そこで、問い合わせ対応の担当を決めておいたり、社内FAQを作成したりすることで、ユーザーの不安を和らげることができます。
また、運用状況を定期的にチェックし、必要に応じてルールや設定を見直すことで、システムの活用度を高めていくことができます。
クラウド型を選ぶときに見るべきポイント
クラウド型ワークフローを選ぶ際は、自社の業務に合った機能性、操作のしやすさ、他システムとの連携性、セキュリティ対応、サポート体制などをバランスよく確認することが重要です。
表面的なスペックや価格だけで判断せず、業務との“相性”を重視した比較が、導入成功のカギとなります。
市場には多くのクラウド型ワークフローサービスが存在し、見た目や基本機能は似ていても、実際の使い勝手や拡張性には大きな差があります。ここでは、導入後に「思っていたのと違った」とならないために確認すべき主要ポイントを解説します。
自社業務に必要な機能が揃っているか
最も基本かつ重要なのが、日々の業務で必要とされる機能が備わっているかどうかです。たとえば、複数段階の承認ルート、代理承認や差し戻しの対応、文書添付、通知設定など、ワークフローに欠かせない要素をチェックします。また、自社特有のルールや運用パターンがある場合には、それをどこまで再現できるかを事前に確認しましょう。導入後に「この機能がなかった」と判明するケースは意外と多いため、要件定義をしっかり行い、それに基づいて選定することが重要です。
UI/操作性が直感的でわかりやすいか
機能が豊富でも、使いにくいシステムでは現場に定着せず、結果として導入が失敗に終わることもあります。そのため、実際に操作する社員の視点に立って、画面の見やすさや操作のしやすさを確認することが大切です。トライアル版やデモを通じて、直感的に申請・承認ができるか、画面遷移に迷いがないか、モバイルからでもスムーズに使えるかなど、実用面のチェックを行いましょう。現場の負担が少ないツールほど、導入後の定着率も高くなります。
他システムとの連携が可能か
ワークフローは単体で完結するものではなく、人事・会計・勤怠・ファイル共有など、さまざまな業務システムと情報のやりとりが発生します。APIやCSV連携が可能か、すでに使っているツールとの互換性があるかなど、システム連携の柔軟性は非常に重要な選定基準です。連携性が高いサービスであれば、申請情報を自動で他のシステムに流し、二重入力や転記ミスを防ぐこともできます。中長期的に見ても、業務全体を最適化しやすい基盤になります。
セキュリティと信頼性に問題がないか
クラウドサービスを選ぶ際は、情報セキュリティの基準が自社の要件と合っているかも確認が必要です。データの暗号化やアクセス権の設定、通信の安全性など、基本的なセキュリティ対策はもちろん、ISO 27001やSOC 2といった第三者認証の取得状況も参考にしましょう。また、データセンターの設置場所(国内/国外)やBCP対策、障害時の復旧体制についても確認しておくと安心です。とくに機密性の高い情報を扱う業種では、この点が導入の可否を左右することもあります。
導入支援やサポート体制が整っているか
導入時のオンボーディング支援や、日常的な問い合わせに対応するサポート体制も、サービス選定において見落とせない要素です。とくに初めてクラウド型を導入する企業では、操作マニュアルの提供や初期設定のサポートがあるかどうかで、導入のハードルが大きく変わってきます。また、利用中のトラブルや仕様の相談に対し、迅速かつ丁寧に対応してもらえるかも長く使ううえでは重要です。カスタマーサクセスを重視しているベンダーを選ぶことで、定着・活用までしっかり支援を受けられます。
これらのチェックポイントをもとに、自社の課題や目的にフィットする製品を選ぶことで、クラウド化の効果を最大化することができます。
実際の製品例:ジュガールの取り組みと特徴
「ジュガールワークフロー」は、クラウド型ワークフローシステムとしての基本機能に加え、現場目線で設計された使いやすさと柔軟性を兼ね備えたサービスです。
導入のしやすさと運用の定着支援に強みを持ち、多様な業種・組織規模で活用されています。
数あるクラウド型ワークフローの中でも、ジュガールは単なる申請・承認の仕組みにとどまらず、業務プロセス全体を見える化・最適化するための実践的な仕組みを提供しています。ここでは、ジュガールがどのような視点で開発され、何が評価されているのかを紹介します。
ノーコードで柔軟なフロー設計が可能
ジュガールはノーコードで申請フローを構築できるのが大きな特長です。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で分岐条件や多段階承認などを設定でき、ITの専門知識がなくても運用部門が自走できるように設計されています。これにより、組織改編や業務変更にも柔軟に対応でき、システム変更のたびにIT部門に依頼する必要がありません。業務に合わせてスピーディーにフローを調整できることは、現場にとって大きなメリットです。
現場の「使いやすさ」にこだわったUI
ジュガールは「シンプルで迷わない操作感」にこだわり、初めて使う人でも直感的に使えるインターフェースを実現しています。申請内容の入力や承認ボタンの配置など、業務フローに沿った自然な導線が設計されており、導入初日から現場で運用がスタートしやすくなっています。スマートフォンやタブレットからの操作性も高く、外出先やリモートワーク環境でもストレスなく使えるのも評価ポイントです。
他システムとの連携性と拡張性
API連携やWebhook対応により、ジュガールは他のクラウドサービスや既存の業務システムと柔軟につなげることができます。たとえば、申請データを会計システムに自動転送したり、人事システムと連動して組織情報を自動更新したりといった運用が可能です。標準機能に加えて、必要に応じた個別カスタマイズにも柔軟に対応しており、自社の業務にフィットした形でシステムを拡張できます。
導入から定着までを支援する伴走型サポート
ジュガールは、単にシステムを提供するだけでなく、導入支援や定着のための伴走型サポートを重視しています。初期設定やトレーニングだけでなく、導入後の運用相談や機能改善の要望にも応える姿勢が特徴で、利用企業からのフィードバックをもとにアップデートが継続されています。導入後の活用度を高めたい企業にとって、こうした“寄り添うサポート”は大きな安心材料になります。
クラウド型だからこそ得られるジュガールの強み
ジュガールワークフローはクラウド型として提供されており、インターネット環境があれば場所を選ばず利用できます。サーバーの準備や複雑な設定は不要で、申し込みからすぐに利用を始められる手軽さも魅力のひとつです。自動アップデートにより、常に最新の機能・セキュリティ対策が反映され、IT部門の負担も最小限に抑えられます。また、スマートフォンやタブレットでも使えるため、外出中やリモートワーク中の申請・承認もスムーズ。ジュガールが多様な働き方やスピード感ある業務推進を支えるのは、まさにクラウド型であるがゆえの特長です。
上記のような効果を、ワークフローシステムを使って実現しませんか?
迷わないためのクラウド型ワークフロー導入まとめ
クラウド型ワークフローシステムは、業務の効率化と柔軟な働き方を実現するための強力なツールです。
ただし、導入を成功させるには、自社の業務に合った機能や運用体制を見極めたうえで、計画的に進めることが不可欠です。
本記事では、クラウド型ワークフローの基本的な仕組みから、オンプレミス型との違い、導入時の注意点、メリットと課題、選定ポイント、そして製品例としてジュガールの特徴までを網羅的に解説してきました。システムの選定や導入にあたっては、機能や価格だけでなく、「現場で実際に使いこなせるか」「既存業務と無理なく連携できるか」といった観点も非常に重要です。
特に初めてクラウド型を導入する企業では、導入後のサポート体制や設定のしやすさ、現場の定着支援までをトータルで考えることが、失敗しない選び方のカギになります。まずは自社の課題や要件を整理し、複数のサービスを比較しながら、最適なパートナーを見つけてみてください。
クラウド型ワークフローは、単なる業務ツールではなく、組織の働き方や意思決定のスピードを進化させる“インフラ”です。
変化に強い組織づくりの第一歩として、今こそクラウド化を検討してみてはいかがでしょうか。